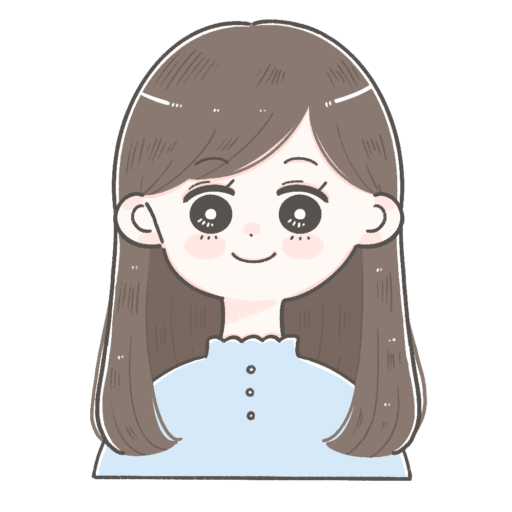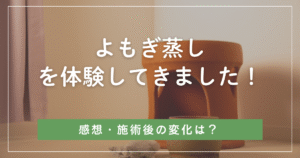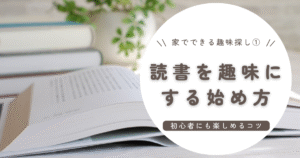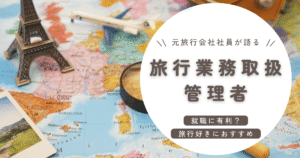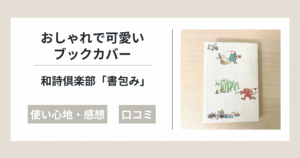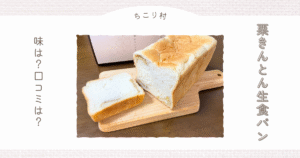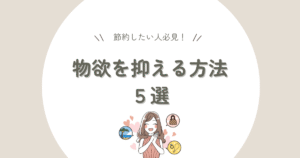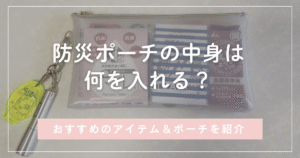こんにちは、Arikoです。
 Ariko
Ariko実は・・・私、今年は本厄の年にあたります。(しかも大厄です…!)
ということで、地元の神社で「厄除祈祷」をしていただきました。恥ずかしながら、ちゃんと厄除祈祷をしたのは初めてです。
.png)
.png)
.png)
厄除祈祷って何をするの?



初めての方は、なかなかイメージしにくいよね。
厄除祈祷って何をするの?どんな流れ?
厄除祈祷をする時の服装・費用ってどうすればいいの?
これから厄除祈祷を予定している方のなかには、疑問や不安もあるかもしれません。
今回は、厄除祈祷の流れや服装について、神主さんから聞いたことなどお話したいと思います。
厄年、厄除け・厄払いとは?


まずは厄年、厄除け・厄払いについてお話します。
厄年
厄年とは、災難や障りが身に降りかかるおそれが多いので、何事においても気を付けなければならないとする年齢のことです。
古代中国の陰陽道を由来とする考えで、日本でも古来より忌み謹んできました。
厄年は数え年で計算し、
男性:25歳・42歳・61歳
女性:19歳・33歳・37歳・61歳
が一般的です。
特に男性の42歳、女性の33歳は「大厄」とされています。また、上記の年齢を本厄と言い、前の年を前厄、翌年を後厄と呼びます。
厄払い・厄除け
厄除け、厄払いとは、厄年を迎えたら、災厄が身に降りかからないよう祈願祈祷を受けることを言います。
厄除け・厄払い
・お寺・・・厄除け
・神社・・・厄払い
・時期・・・厄年になった年のお正月から節分(2月3日)までの間に参拝して受けるのがよい
※厄除けと厄払いは、特に区別のない寺社もあります。(私は神社で行いましたが、神社の祈祷の名目としては「厄除祈祷」でした)
どちらで行っても構いませんので、菩提寺や自分の好きな神社などで祈祷してもらいましょう。
また、時期についても厳格な期限ではないので、過ぎても可能です。
厄除祈祷の流れ
- 2月初めの平日、午前10時開始で申し込み
- 実家がある地元の神社
祈祷の時間自体は約15~20分、受付や待機の時間を含めても約30~35分でした。
1.受付
ご祈祷が始まる15分前に受付を行いました。
事前にホームページで氏名、住所などを記入して申し込んでいたので、当日は内容の確認と初穂料のお渡しのみでスムーズに受付ができました。
2.お清め


受付が終わったら、境内にある手水舎で手を清めます。
- 右手で柄杓を持って左手を清める
- 左手で柄杓を持って右手を清める
- 右手で柄杓を持って、左手に水を受けて、口を清める(衛生面が気になる場合は口を漱ぐ真似でOK)
- 左手を再度清める
- 杓を立て持ち手部分を清める
3.待合室で待機
お清めが終わったら、神社の待合室で時間になるまで待機します。私は平日の午前中に行ってもらいましたが、幸いなことに私1人だけでした。
時間になると神社のスタッフに呼ばれるので、指示に従い、社殿に上がります。
4.祈祷
社殿に入ると、厄除祈祷が始まります。
以下は、私が行った神社での流れです。一般的には多くの神社で以下のような流れで行われると思いますが、一部違う流れで行われる神社もあるかもしれません。
厄除祈祷の流れ


まずはお祓いの儀式・修祓(しゅばつ)が行われます。
修祓は、神主が祓詞(はらえことば)を読み上げ、大麻(おおぬさ)で参拝者のお祓いをします。
受ける側は、頭を下げたままお祓いを受けます。
お祓いの後は、神様と参拝者の間を執りもつ祝詞(のりと)が読み上げられます。参拝者のお願いごと、住所氏名を神様に申し上げるものです。
祝詞を奏上する間は、参拝者は頭を下げます。


祝詞奏上の後、お鈴でお祓いが行われます。
受ける側は、頭を下げたままお祓いを受けます。
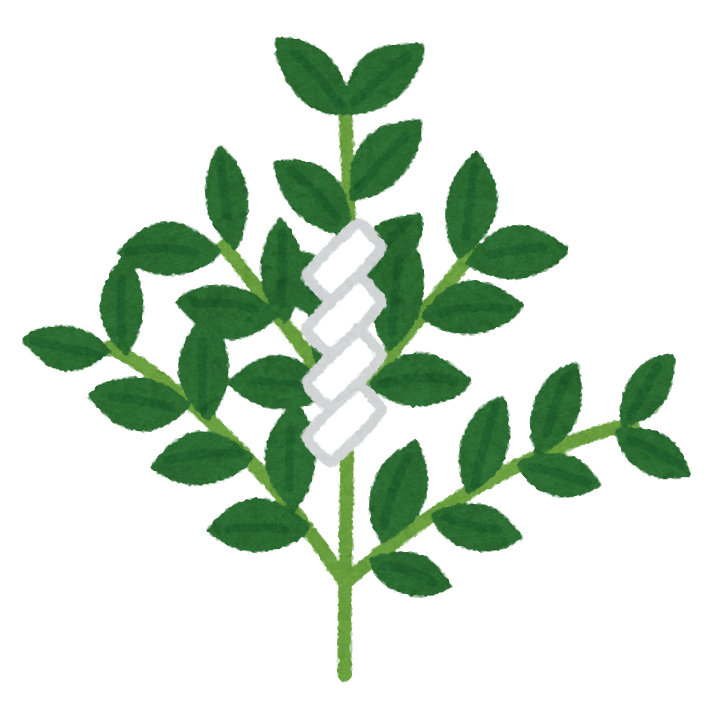
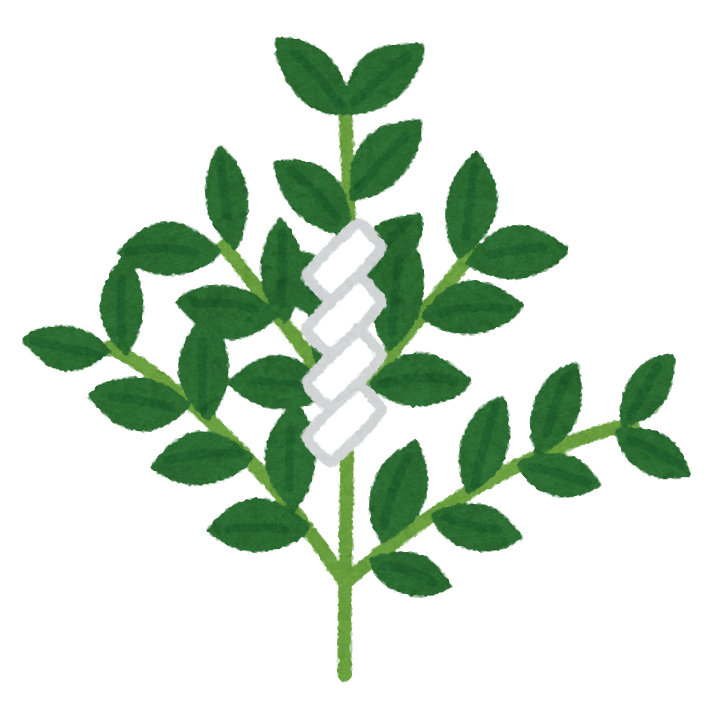
祈祷の最後に、玉串を神様にお供えして拝礼をします。
玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)をつけたもので、根元を神様の方向に向けお供えします。拝礼は「二礼 二拍手 一礼」です。



神主さんなどが教えてくださるので、心配しなくても大丈夫です!
5.神主さんからのお話
祈祷が滞りなく終わった後は、神主さんからのお話がありました。
今回は厄除祈祷なので、厄年に関するお話をしてくださいました。
6.撤下品授与
神主さんからのお話が終わると、撤下品が授与されました。お札、お守り、手ぬぐい(開運干支手拭)が入っていました。
厄除祈祷の費用は?


ご祈祷のお礼として神社へ祈祷料を渡しますが、これを「初穂料(はつほりょう)」と言います。
初穂料
初穂とは、神仏への捧げ物となる稲や穀物などの農作物のことで、その年初めて収穫された稲穂(初穂)をお供えしていたことが由来です。
初穂料の相場は地域や神社にもよりますが、5,000円から10,000円とのことです。
ちなみに、私が祈祷を行った神社では、最低6,000円から、8,000円、10,000円、15,000円、20,000円、30,000円、これ以上はお気持ち、という感じでした。



私は6,000円を納めました。
祈祷を受ける時の服装は?


指定の服装はありませんでしたが、「神前のため礼を失しない服装で」という案内がありました。
カジュアルすぎる服装、裸足はNGでした。
・男性:スーツ、シャツにスラックス
・女性:ワンピースやオフィスカジュアルなど
決まりはないですが、上のような服装が無難かなと思います。
派手な色合いは避け、女性の場合、スカートやワンピースの丈は短すぎないものにしましょう。
ちなみに私は、以下の写真のような服装で行きました。


厄年は悪いことじゃない!お祝いだった!?


せっかくなので、神主さんから聞いたお話を皆さんにも共有したいと思います。
厄年と聞くと、皆さんはどんなイメージを持たれますか?
.png)
.png)
.png)
「良くないことが起こる」「悪いことが起こる」というイメージ・・・
あまり良くないイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。
でも、実は厄年って悪いことではなく、お祝いだったそうです。
厄年はお祝い!?どういうこと?
昔の日本では・・・
・寿命が今よりも短い。当然、成人するのも早い。
・男性だとだいたい15~17歳で元服(げんぷく)、女性だと12~16歳に裳着(もぎ)を行い、一人前の大人になる。
・成人すれば、次は結婚と出産。
・結婚年齢も出産年齢も今では考えられないくらい早い。
・子育てをして、その子が成人する時には30代。
・昔は30代で人生が一段落。
成長していく中での人生の節目の年、本来、厄年は「ハレ」として捉えられていたそうです。
そして、男性の42歳が初老とされるように、「ここまで生きることができたね」というお祝いの年。
地域によっては、厄年にお祝いをする風習が残っているところもあるそうです。
現代の日本は・・・
寿命もライフスタイルも変わりました。
身体的・精神的・社会的に変化が起きやすい年齢でもあることから、いつしかお祝いとしての意識は薄れ、忌み慎む意識だけが残っていったそうです。
厄年には慎ましく生きることが大事だけれど、本来はお祝いだったって思えば、気にしすぎたり、必要以上に心配することもないのかもしれませんね。



お話を聞いて、厄年のイメージが変わりました。
まとめ
今回は厄除祈祷に行ったお話しました。
- 厄年とは、災難や障りが身に降りかかるおそれが多いので、何事においても気を付けなければならないとする年齢のこと。
- 厄除け、厄払いとは、厄年を迎えたら、災厄が身に降りかからないよう祈願祈祷を受けること。
- 厄除祈祷の一般的な流れ:①受付→②お清め→③待合室で待機→④祈祷(修祓→祝詞奏上→鈴祓い→玉串拝礼)→⑤神主さんからのお話→⑥撤下品授与。
- 厄除祈祷の費用(初穂料)の相場は、地域や神社にもよりますが、5,000円から10,000円。
- 祈祷を受ける時の服装は、男性:スーツ、シャツにスラックス、女性:ワンピースやオフィスカジュアルなどが無難。
- 厄年は本来お祝いで、「ハレ」として捉えられていたそう。
.png)
.png)
.png)
気に病みすぎずに過ごすことが大事なのかも。



「笑門来福」―笑う門には福来たる。
謙虚に過ごしながらも、笑って過ごしたいよね。
厄年に科学的根拠はありません。なので、祈祷に行くもよし、行かないもよし、です。



厳かな雰囲気や神主さんのお話が聞けたりと、私は行って良かったなと思っています。